
自動車業界など製造業(メーカー)では、非常に多くの業界用語があります。
そこで本記事では、自動車メーカーや自動車部品メーカーなど製造業に就職をお考えの方や、すでに自動車業界など製造業で働かれている方に向けて、業界の用語集をまとめました。
なるべく柔らかい表現で分かりやすく表現するように気を付けています。
ぜひ本記事を参考にし、製造業で使える用語について学び、業界で活躍できる知識を身に付けて下さい!
※本記事と共に読みたいおすすめ記事はこちら!





ISO
ISOは、International Organization for Standardizationの略称で、日本語では、国際標準化機構が定めた国際規格のことを指します。
平たく言うと、世界中を通して、共通の規格や認識を持った方が都合が良いものを標準化して保証するのがISOです。
ISO9001
ISOには様々な規格がありますが、その中でも有名かつ重要なのが、ISO9001です。
ISO9001とは、国際標準化機構(ISO)による品質マネジメントシステムに関する国際規格です。
もう少し平たく言うと、製品やサービスを作り上げる工程や作業環境の管理方法を標準化する仕組みを指します。
それでも分かりにくいと思いますので、例を挙げます。
例えば、「紙で鶴を折ってください」というお題が出されたとします。
それだけだと、人によって、折り紙を使う人やただの紙を使う人、黒色や黄色で作る人、折り方や折る順番が異なる人が出てきて、出来上がる鶴は、人によって全く異なる仕上がりになります。
その反面、使う材料や折り方などについて、詳細な指示があれば、出来上がりの鶴は、限りなく同じものに近づきます。
しかし、それでも求めている鶴と異なる鶴が出来たときは、その原因を明らかにし、対策を取る必要があります。
このように、ISO9001とは、「品質を守る手順書を作り、さらに不具合が発生した場合に継続的に改善していくための仕組みを作ろう」という、品質マネジメントシステムに対する規格のことです。
ISO/ TS16949
ISO9001をベースに、自動車業界特有の要求事項を加えた規格として制定されたのが、ISO/ TS16949です。
自動車産業界における品質マネジメントシステムの要求事項を定義しています。
今や、IATF16949が最新ですので、そちらの項目を参照下さい。
IATF16949
自動車産業界における品質マネジメントシステムの要求事項を定義しているISO/TS16949に代わる規格が、IATF16949です。
IATF16949の目的としては、欠陥の防止やサプライチェーンにおけるムダ及びバラツキの低減など、品質マネジメントシステムを継続して改善していくことです。
IMDS
IMDSとは、International material data systemの略称であり、日本語では、国際材料データシステムと呼ばれます。
IMDSは、自動車業界の材料に関する共有のデータシステムのことであり、主に環境を保護するために規定された各種法律に対応することを目的として、自動車メーカーが活用するものです。
PPAP
PPAPとはピーパップと読み、もちろん、ピコ太郎のペンパイナッポーアッポーペンとは異なりますよ。笑
PPAPは、Production Parts Approval Processの頭文字を取った略称であり、直訳すると、「生産部品承認手続」という意味を持ちます。
自動車メーカーが、自動車部品メーカーなどから部品や材料などを購入する際に承認する手続きのことです。
特に、アメリカ自動車工業会(AIAG)が発行しているPPAPというマニュアルに則って進める北米メーカー(GM、FCA、Fordなど)が主です。
ISIR
ISIRは、Initial sample inspection reportの略称であり、日本語では初品検査成績書を指します。
PPAPと同じく、自動車メーカーが、自動車部品メーカーなどから部品や材料などを購入する際に承認する手続きのことです。
但し、PPAPと異なり、ISIRは欧州メーカー(BMW、VW、DAGなど)が主となっています。
DV評価
DV(Design verification)評価とは、試作品での評価を指します。
自動車メーカーと自動車部品メーカーの間で、承認図を取り交わして量産立ち上げする前に、試作品で自動車メーカーが要求するスペックを満足するか確認するために、DV評価が実施されます。
PV評価
PV(Process verification)評価とは、量産品での評価を指します。
量産品でも、試作品で実施した評価(DV評価)通りの結果が得られ、自動車メーカーの要求するスペックを満足できるか確認するために、PV評価が実施されます。
DR(デザインレビュー)
DR(デザインレビュー)とは、日本語では設計審査と呼ばれ、設計の企画から基本設計、量産段階など、各段階で設計内容が適切か確認するために行われます。
シンプルに言うと、設計や量産した時に何か問題が発生しないか、関連部署の方々と議論し、不具合を未然防止しようという目的で行われることが多いです。
日産では、全く新規の設計に関してはフルDR、一部の設計変更にはクイックDRという変化点に特化して考えることで効率よくDRを進めるという手法を採用しており、自動車関連のメーカーから注目されていますね。
SOP(Start of production)
英語の通り、量産体制での生産開始を表します。
号口やLO(Line off)という呼称が使われることもあります。
下記しますが、EOP(End of production)の対となる用語です。
EOP(End of production)
英語の通り、量産体制での生産終了を表します。
但し、自動車業界では、EOPを迎えても、補修用などとして、自動車の各部品メーカーは自動車メーカーに部品を供給することが義務となります。
なので、EOPになったからといって、すぐに廃版となるわけではありません。
(もちろん場合にもよりますが。)
NDA(Non disclosure agreement)
NDA(Non disclosure agreement)とは、日本語では秘密保持契約という意味になります。
営業秘密や個人情報といった個人情報を第三者に開示しないように、法人間で締結する契約のことを指します。
RFQ(Request For Quotation)
RFQ(Request For Quotation)とは、日本語で見積依頼書のことを指します。
調達における引合いプロセスの主要な書類で、名前の通り、見積りが記載されています。
また、自動車メーカーなどが、複数の自動車部品メーカーから、サプライヤーとして採用する取引先を決定するために、ちゃんと正式な手順を踏んで検討して決定しましたよという保証にもなります。
D-FMEA
D-FMEAとは、Design failure mode and effect analysisの略称で、日本語では、製品設計の故障モードと影響解析のことを指します。
まあ、実際にD-FMEAを作ったことや見たことがない人には、理解し辛いです。
D-FMEAは、製品の構成部品毎に、発生しうる故障モードを予測し、事前に対策をすることで、設計段階で故障モードを未然に防止するためのツールです。
もう少し平たく言うと、みんなで、新規設計品で発生しそうな不具合を予想して挙げていき、その不具合が出ないようにするには、どのように工夫すれば良いだろうということを考えていくことです。
新規設計品をそのまま生産段階まで進めていくと、様々な不具合が発生し、場合によっては設計からやり直しとなり、手戻りのムダが発生します。
そのような事態を防ぐために、D-FMEAは重要となります。
P-FMEA
P-FMEAとは、Process failure mode and effect analysisの略称で、日本語では、製造工程の故障モードと影響解析のことを指します。
D-FMEAと同様、実際にP-FMEAを作ったことや見たことがない人には、理解し辛いです。
P-FMEAは、製品の製造工程毎に、発生しうる故障モードを予測し、事前に対策をすることで、設計段階で故障モードを未然に防止するためのツールです。
もう少し平たく言うと、みんなで、新規設計品の製造工程において、発生しそうな不具合を予想して挙げていき、その不具合が出ないようにするには、どのように工夫すれば良いだろうということを考えていくことです。
D-FMEAと異なる点としては、D-FMEAは製品の設計段階であり、P-FMEAはその後の量産時に使用されるというところです。
アウトソーシング
アウトソーシングとは、仕事をする人やサービスなどを、契約によって外部から調達することを指します。
まあ要するに、人手や技術などが不足しているなどの理由で、お金を払う代わりに、その不足分を他者から借りるというイメージで問題ないです。
その他にも、自社内でやるよりも外部の専門家に委託した方が安く済む場合や、付加価値の低い簡単かつルーチン的な仕事を任せる時にも、アウトソーシングは活用されます。
過去トラ
自社内や関連会社、取引先で発生した不具合などのトラブルについて、その発生状況や原因、その時に実施した対策などをまとめたものです。
過去トラは管理台帳として保管され、類似の不具合が発生してしまった時に活用されます。
原価
原価には様々な種類がありますので、下記します。
・工場原価:加工費+材料費
※加工費:製品を作るための人や機械の費用
・製造原価:工場原価+工場管理費
※工場管理費:技術部門などの間接費
・総原価:製造原価+広告費などの営業費
・総々原価:総原価+関税や輸送費などの費用
※本記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、下記のシェアボタンで、ぜひ本記事をみんなにもシェアしてあげてください。
ー以上ー
※本記事と共に読みたいおすすめ記事はこちら!





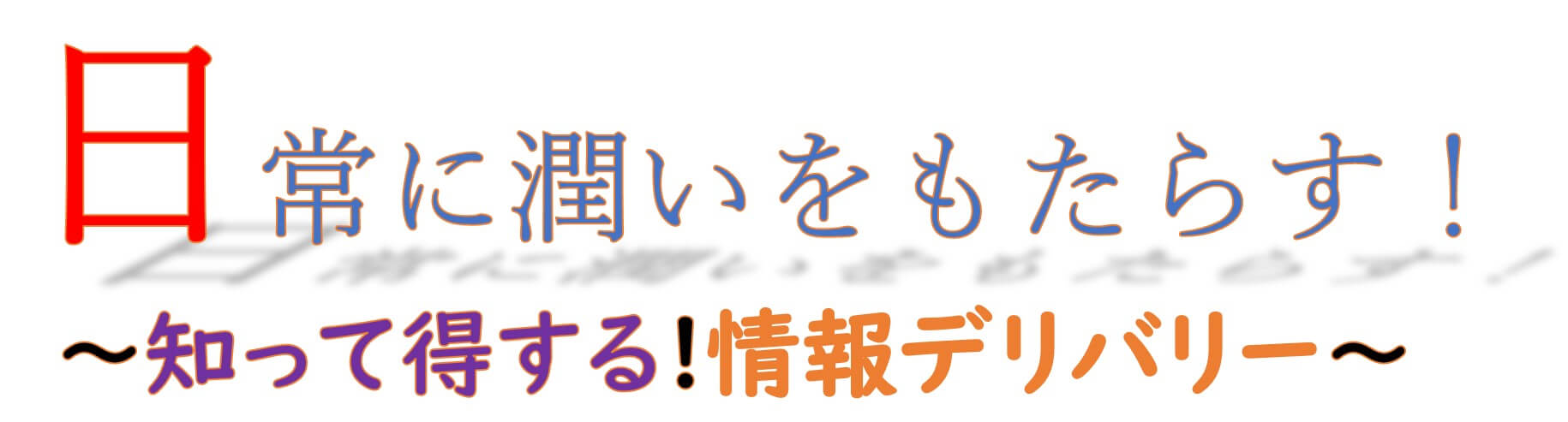
コメント